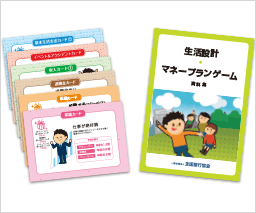金融経済教育の5時間目は「信用」について、6時間目は「契約」についての授業が実施されました。 ローン・クレジットについて学んできた生徒たちは、計画的にお金を借りること、ローン・クレジットのメリット・デメリットについては十分理解できています。さらに、お金を借りる際に必要となる「信用」と「契約」について学んでいきます。
赤澤先生から、資料を活用してポイントを端的にまとめる作業は、単に資料を読むよりも情報を頭の中に定着させていくことができるということが、再度説明されました。授業が進むうちに、ポイントを分かりやすくワークシートにまとめられるようになってきました。ポイントをまとめた後は、各班で発表していきます。
5時間目授業では、ローン&クレジットのABC p17のQ6に合わせて、①自分たちが持っているカード・例えばどんなカードを持っているか、②自分たちが持てないカード・なぜ高校生はそのカードを持てないのかの理由、を発表していきます。
| ・プリペイドカード | 琴電乗車券(カード式)・図書カード | 持てる |
|---|---|---|
| ・キャッシュカード | 銀行や郵便局のカード(口座があれば) | 持てる |
| ・IDカード | 学生証 カラオケのメンバーズカード | 持てる |
| ・デビットカード | 代金が口座から直接引き落とされる機能 | キャッシュカードと同様 |
| ・クレジットカード | 学生は持てない ← | 信用がないので持てない |
| ・ローンカード | 学生は持てない ← | 信用がないので持てない |
また、お金を借りる人の信用を表す4つのC(人格Character、資産Capital、支払能力Capacity、自己管理Control)のなかでも、特に「支払能力」と「資産」が重要になることが赤澤先生から説明がありました。
最後に、班ごとに本時のまとめを行い発表しました。
- 人と人との信頼関係は、日々の積み重ねから
- 与信とは、お金を貸す相手への信用を供与すること(信じること)
- 暗証番号は、人に知られにくいものにしないといけない
- 連帯保証人になった場合には、借り主とほぼ同等の責任を負うことを知っておくこと
- 担保には物的担保と人的担保があること
- キャッシュカードやクレジットカードを不正に使用する事件が増加しているため、ICチップを埋め込んだカードが増えてきている
6時間目授業では、はじめに赤澤先生から「契約」とは専門用語であり、二人以上の当事者の意思が合致して成立する法律行為であること」が説明されました。
p20~23で調べ学習を進めていくなかで、多くの生徒たちが驚いていたのは「コンビニでの買い物も売買契約にあたる」ことや、「レストランで食事をする」「DVDをレンタルする」「携帯電話を使用する」のなど日々の生活で行われているほとんどの事象が「契約」の範囲に含まれるということでした。
授業のはじめに赤澤先生が説明した「二人以上の当事者の意思が合致して成立する法律行為である」という意味が少しずつ理解できてきたようです。また、今まで学んできた預金やローンについても、銀行との契約にもとづいて行われていることを学びました。
日常生活の様々な場面に契約が存在しており、契約の後ろには法律があるということ、契約は双方にそれぞれやるべきことがあるので、自分の立場を理解して行動することが大切であり、この行動こそが信用につながることが理解できたようです。
また、ここまでの授業内容について振り返りとまとめの作業も行いました。
生徒の感想
- テキストには大事なことがたくさん載っていて、分からない単語を調べたりするのはとても大変で す。これから進んで行く授業の中で分からないことがあったら、すぐに調べて理解できるようにし たい。
- 全体的に知らないことが多かった。金融経済は社会に出るために必要なことだと思うので、それま でに身につけておきたい。
- 自分が知らなかった事を多く知ることができ、自分の将来に活用できると思う。またもっと多くの 知識を得ることで、より多くの場面で活用できたらいいと思います。
次時からの授業に向けて、なぜ金融経済に関する知識を身に付ける必要があるのか、これからどのように学んでいきたいかなど再確認することができたようでした。